中国、韓国、日本を中心とする東アジアの2000年間の領土の変遷を動画で見られる。
歴史の勉強はつまるところ地図と年表だと思っていたが、こうして動画で見られるのは素晴らしい。
他のエリアの領土変遷動画も探しておきたい。
中国、韓国、日本を中心とする東アジアの2000年間の領土の変遷を動画で見られる。
歴史の勉強はつまるところ地図と年表だと思っていたが、こうして動画で見られるのは素晴らしい。
他のエリアの領土変遷動画も探しておきたい。
ノート術をまとめてみた。主に大学生や高校生などの学生の授業ノート作成法を想定して書いているが、サブノートやアイデア帳、会議でのメモなどにも有効だと思う。
なりよりもノートの技術は、そのまま学習のためのメソッドの柱となる。効果は非常に大きいと思うので、一度しっかりと考えてみるとよいと思う。
まあ、「今、目の前だけ見てろ」と。つまり妄想に耽るなということ。
人類の異常な咽頭の発達が言語を生みだし、その記録から文字が生まれたとする、まあ、よくしらんけど。そして、その言語が文字に記録される中で形式化が進んだ、と。んでもって、その「言語の形式化」の中で思考も形式化を求められていった、と。そして、その形式化していった思考ってのは、ちょっと現実とズレがあったりして、その辺が、少年少女には苦しかったりするんだろうな、と。
ま、言葉は結局、言葉で鳴き声の延長でしかない。むしろ、その鳴き声が、「記録」や「反省」などによって、ここまで「言語思考」「論理思考」などとして形式化していった事の方が驚き。そして、その「思考」の中にのみ善悪や美、真理などの抽象概念がありえる訳だからややこしくなり、そういう観念や論理に悩むことは悩むということかと。
俺的には、こうした惱みは「病気」「欠点」って感じじゃなくて、「成長痛」のようなもんかと思う。人間、言語や論理、抽象的思考なんかを使えた方が便利な訳で、その道具の習得には、まあ、ある程度のケガは仕方ないなと。んで、使えるようになると、やっぱり便利な道具だな、とか思うわけだし。思考とか、抽象ってのは。あ、芸術とかもいれとく。
まあ、でも、それはそれとして、つまり道具として使わんといかんわけで、だんだんいいとしになると、それでケガすることも減るようになるんだと思う。だから子供は多いに抽象概念に迷い、苦しんでみて、大人を憎しみに満ちた目で睨んで「テメーラ、マチガッテル!」と叫べばいいんだと思う。そうして培った能力が未来を作るんじゃねーの? しらないけど。
ま、そんなこんなで抽象的なことに悩んだりして、最終的には「やっぱ、目の前しかありえない」ということになったりするんだと思う。時間は流れないし、過去も未来も実在しないし、自我も実在しないし、いかなる「本質」は実在しないし、いかなる抽象概念も実在しない……などなど。ただ、その場その場でありのままにあることしかなく、そうであるなら、ただただひたすらにやっていくしかない、ということになる。
かくして「世界は無である」ということに。ただ、その場、その場があるだけ。んで、その場ってのは? と思っても「そりゃ、場は無ですよ。何かが「ある」場なんて場じゃないでしょ」ということに。
はい。ここまでが第一段階。
んで、第二段階として、その実在しないものごとを実在しないと理解する訓練の段階があるのかと思う。これが、いわゆる精神的とか宗教的というやつかな。スピリチュアルとも言うのかな。でも、一般的な響きとは逆で、俺は、こうした修行・訓練は、形而上的なものや抽象的なものの「非実在」を体得するために行うんだと思ってる。「あ、やっぱ無だな」と普通に実感できるようにするために、瞑想とか禅とかしている。というか「ために」ってのもおかしくて、言葉、論理や概念で差されたものが無であることを実感するためなんだから、「ために」ってのはおかしい……いや、だから、「ために」ってのはおかしいんだよ……って無限矛盾の連鎖……。
かくして、自我/自己も本質も世界も何もかもが、まあ、なんでもない、ただの言葉として吹きとんでいくことになると思う。方法はよく分からんのだが、知覚のスピードが高速になると、対象知覚から概念形成の間の一瞬を気づけるようになるんじゃないかと思う。足元に黒いものが動いてて、虫かと思って「うわ」っと思ってのけぞったら、ただのゴミが風で飛んでただけだったとか、そういう知覚(この場合、色と運動)と認識(虫)の差をリアルタイムに認識できるようになるんじゃないかと思う。ようわからんけど。
そうなると周囲の変化に動じなくなる。何しろあらゆる無意識の意味づけを排除して反応できるんだから。
ここまでが、俺の求める第二段階。
んじゃ、第三段階ってのは何?思うんだけど、第二段階までで、妄想を離れてその場その場に没頭できるようになると、逆に従来ではなかった知覚も現れ、様々な現象を正確に把握し、それを制御できるようになるんじゃないかと思う。まあ、よくわからん。こうなるとヤバヤバだから、まあ、どうでもいいや。以上。
えーと、第2段階は具体的には瞑想でしょうね、きっと。別に妄想を拵えるために坐るんじゃなく(「無」とかも妄想なんで)、ただ、ひたすら、心の変化を観察するんです。そうすると人間が実際に疑いようもなく感じるものは直感のみであること、心は変化し続けることに自然に気がついてゆくんじゃないでしょうか。「ああ、何も確かなものはなく、あるのは移り変わるいまここだけだ。記憶も不安も妄想であった」とね。
そうした心の意識的な観察で「純粋知覚」→「概念表象」→「嫌悪や欲望」→「行為」などの流れを感じると思うんです。そして、その流れを見て「ああ、自分はこういう知覚の時、こういう概念化をしやすくて、そいつがこういう嫌悪や欲望を生んで、こういう行動になるという傾向があるんだな」とか直感的に思い付けばいいんだと思います。この自分の奥に潜む「傾向」を感じてゆくと、まあ、いわゆる魂ってやつは救われるんじゃないかな、と。
そうした心に対する観察を常に続けながら、つまり、気づきながら生きることが、2段階の完成になります。心を観察し続けるから、最初は離人症みたいな感覚を覚えるかもしれませんが、慣れると「私は心身を離れている」ことが当然になり、欲望や嫌悪が遠くなるので、生きるのが非常に楽になりますよ。まあ、常にってのは、私はまだ出来てませんが。
無駄に音楽の自分の音楽の背景なんかをぼやいてみる。
自分はギターを弾く。その中でブルースとフラメンコに強い興味を持った。この二つはかなり自分なりにコピーをしていった。
だからロックを弾くにしても、その二つの影響が必ず出てくる。ロックのビートでブルースっぽく弾くと、いかにもブルース・ロックのペンタ一発みたいになるし、フラメンコっぽくなると、どことなくサンタナっぽくなる。どちらも嫌いじゃない。でも、別に深入りするほど好きじゃない。考えてみりゃバンドしてる訳でもないから、やる機会もないし。
ロックをやるのならパワーコードだけでおしまいになるような曲の方が好きだ。ニルヴァナのスメルズとか、ポリーを一人寂しく口遊んでみたり、叫んでみたりする。ただ、ほんとうに、タマにだ。
あとは、パコのアルモライマのブレリアスの半端なコピーをたまに弾く。ブレリアス以外には最近は弾かない。大学時代にはセビジャーナス、タンゴス、ソレアスなどもやったが疎くなった。やはり、踊りと唄がないとフラは話にならない。楽しくない。
ブルースをなんとなく弾く。中学校の時からのhey, heyやbefore accuse of me なんかのクラプトン、アンプラクトのコピーをポロポロと弾く。クラプトンなんて馬鹿にしてるんだが、どうも始めが彼だったから手になじんでしまっている。それに「白人のブルースは駄目だ」なんて言う元気も、もうないよ。
あとRJの数曲、サンハウスのデスレター。ただ、デスレターはテンション高くないと弾けないから、あまりやらない。それに調弦変えなきゃならんし。なんとなくで、RJのsweet home chicagoを唱う。せつない。でも、ざっくざっくと前に向かう気はする。あと、ジミヘンをアコギで静かに弾く。リトルウィングとかヘイジョーとか。
他に大学時代にボサノヴァのサークルにもいさせてもらったので、ボサノヴァも弾く。これが恥ずかしながら、結構好きだったりする。同じくジャズも恥ずかしながら、たまに弾きたくなる訳で、そういうジャズなコード進行をボサノヴァっぽく弾くのは、結構好き。実は口では馬鹿にするが、結構好きである。そういえば、一時はウェスやジャンゴのコピーもしてたが、全然弾かないなあ。
最近は「You'd be so nice to come home」を一人寂しくボサっぽく弾いてみたりする。そして、大学時代のボサのヴォーカルの女の子を思い出したりもする。女の子の伴奏は楽しかった。
フラメンコでも唄と踊りの伴奏は楽しかったし。また、やりたいが、機会はないだろうな。
思い出すと迷惑かけたことしか出てこない。本当に申し訳なかったと思う。
最近は琵琶とか三味線っぽいフレーズを取り込みたいと思っている。案外すんなりとギターでも琵琶フレーズは弾ける。ただ、ギターは「さわり」がないから独特の「ビーン」という音にならない。ギターでの琵琶や三味線の物真似はむなしい。
なんだか、根無し草だな、とか。一つの自分の土着の音楽をやれてたら、どんなにか、楽しかったろうな。
なんだか書くこともないので、いつものようなことを書いてみる。
結論を先渡しすると「自分を常に観察できるようになれば、振舞が意識的になり、自然に行動が完璧に近づく。行動が完璧になれば人間関係の問題と自己認識の問題は解決するはず。特に、人と会話している時に無意識的になりやすいので注意が必要」といういつもの話。それで「その観察の基礎力を付けるために観察瞑想で洞察力を磨け」ということ。
常に自分に常に気づきながら、完璧に動作する。全てを洞察する。これにつきるのだろうと思う。
人の悩んでいるのを見ていると、だいたい人間関係か自意識の問題である。つまり、人間関係や自意識をどう認識して処理するかで苦悩するのである。
大まかな感覚で言うと、女性は「誰誰さんがどう思ってる」「どうして、こんなに頑張ったのに報われないの?」「誰誰さんが羨ましい」という人間関係に苦悩しているように見え、男性は「自分が仕事を続けることに意味はあるか?」「そもそも生きるとは何か?」「自分とは何か?」などの、自己認識についての苦しみをしているように見える。勿論、安易な性別論はよろしくないが。
こう書いて気づくが、本質においては、両者の問題は一致しているのだろう。自意識があるからこそ、その自意識が人間関係上で達成されないと苦しいのだろう。そうした人間関係と自意識のズレの問題を、人の方に問題があると考えれば人間関係の惱みになるし、自分に問題があると考えれば自意識の問題になるのかもしれない。
悩んでいる本人にはかわいそうなことに、こうした苦悩は無駄な悩みに見えることが多い。本人が勝手に悩み苦しんでいるように傍からは見えるのである。
この苦しみは不必要であると他人に見えるからこそ、泥沼にはまり、苦しみとなるのかもしれない。
この問題はとても苦しい。答もないので、いつ終わるかも分からない。どちらが、より苦しいかは分からない。
では、人間関係を捨て、自己認識をしないようにすれば苦しみは無くなるのか?
そうではないだろう。まず、この解決法は現実的ではない。人との交流を断った上、更に思考を放棄するための特別の努力が必要である。始めからそれほどの計画を着実に実行できる人ならば、人間関係で苦しむことはようにも思う。また、単に人間関係を捨てただけでは、逆により強固に、「人の声」や自己認識の苦しみに襲われるものである。
結論的に言うと、私たちは人間関係と自意識を捨てられないのだから、その問題を制御する能力を高めねばならないだろう。
その修行方法はというと、やはり徹底的に人間関係と自己認識に苦しむより他はなかろう。しかし、ただ、漫然と苦しむのではない。意識的に観察し続けるのである。己の苦しみを冷徹に観察し、苦しみの原因を分析するのである。
人間関係や自己認識に苦しむのは何故だろう?
一つには自分が自分の思うような状況で暮らせられないということとがあると思う。
ならば、完璧を目指すのが一番簡単なのではないか、と思う。つまり、人の目を気にしないように努力するよりも、どう見ても完璧に生きるように努力してみるのはどうだろうかと思う。
「それができないから苦しい」と思うかもしれない。確かに、その通りである。
ただし、その見方は自分の目であるとしたらどうだろう。
それでも大変だと思うかもしれない。しかし、ここで考えて欲しいのは、何故、自分の目から見ても不満な生き方を人はしてしまうのかということである。
人は無意識の内に行動をしていて、後から「良くなかった」と考えるのではないかと思う。つまり、行動しているまさにその時には無意識なのではなかろうか。そうでなければ、自分にとって不満な行動をし続けているというのは説明しにくい。
つまり、自分の目で見て完璧に暮らせるためには、まず、常に自分で自分を監視できる必要があるのである。そして、常に監視が十分にできているのなら、自然と完璧に行動に近づくのではないかと思う。人が間違うのは無意識に惰性の行動をすることによってであると私は思う。
もし、常に自分で自分を監視できるのならば、自分で自分を完璧にしようと思うだろう。何故ならば監視しているのが自分なのだから。通常は自分が「監視されている」と思ってしまうので、監視される、完璧に暮らすというと窮屈な気分になるのだろう。
監視されて暮らせということではない。自分で積極的に監視しろということである。そして、自分で自分を監視し続けられるのなら、自分のことを完璧にするだろう。そういうことである。
だから、まず完璧にすることを努力するのではない。自分を24時間監視できるように努力するのである。その監視ができるようになれば、行動は自然に改まるだろう。
そして、その自分で自分を監視するために、人を「利用」するのである。人と話している時というのは最も意識が「お留守」になりやすいと思う。話題に没入してしまうのだ。そうした人と話している時にこそ、自分を監視する練習をすればよいと思う。
いや会話の時だけではないかもしれない。食事もそうだろう。食事の時に「味わっている自分」を観察するというのは難しい。だから、何か自分が没入しやすい行動をしているときにこそ監視ができるように練習するとよいと思う。
ただ、そのためにも監視しやすい状況での練習が大切とは思う。具体的には座って瞑想することである。座って静かにしていても観察できないのでは、他の行動をしているときに観察するのは不可能である。まず、しっかりと時間を取って坐り、自分を観察するとはどういうことかを学ぶ必要があるだろう。
そして、常に監視できるようになれば、自分の行動が人にどう見えるのかも分かるのだから、人から見ても完璧になる日は近い。そうすれば、様々なことに気がつく。「ああ、こういう仕草をしたら、この人はこう思うのだな」「こういう動作が影響がありそうだ」こうした些細なことを観察できるようになる。分析というよりかは直感的な理解である。
そして、人に会っている時にも、常に自分の観察の下に行動できるようになる。
自分に常に気づきながら、完璧に動作する。全てを洞察する。これにつきるのだろう。
3つの秘訣は以下。
それで「ここまでの結論・・・睡眠+心理カウンセリングが最強の組み合わせ」とのこと。
1つの結論は【いにしえの智慧と技に学ぶ】であり
そんなお釈迦様の伝えられた菩薩道。とのこと。
その身は「無為自然無極の体(脱力)」であり、その心は「柔軟心」と呼ばれます。
五体投地で溜まったストレスをふるい落とし、どんなストレスにも固まらない柔らかい心を手に入れる。
ん? よく分からないんだけど、五体投地すればいいのかな? まあ、確かに、あれはよさそうだ。
ちなみに以下のストレス解消法の分類は参考になりそう。
1.体を動かしてリラックス(スポーツ、ストレッチ、など)
2.体を休めてリラックス(お風呂に入る、寝る、など)
3.心を動かして癒される(大声を出す、泣く、など)
4.心を休めて癒される(音楽を聞く、自然を眺める、など)
心身を緊張させ、弛緩させるという4段階のストレス解消法が理想なのでは?
地デジに興味があるのだが、
要するに、最初から最後まで役所とテレビ局と電機メーカーの都合だけで計画を進めてきて、土壇場になって消費者がついてこないことに気づいてあたふたしている、という日本の産業政策の失敗の典型だ。とのこと。なるほど。
以前にNIKKEI NET(日経ネット): 総務省、格安チューナーの開発を要請へ・1台5000円以下でってニュースを読んだが、まあ、いかにも大変そうだ。どういう所で落ち着くんだろう。
私は医者でも何でもないが、鬱病患者を「看病」する上で必要と思える考えについてメモをしておく。くれぐれも自己責任で。
「看病」は長期戦である。相手を大切にする気持ちは大切だが、自分が倒れたら共倒れになる。相手に頼れない以上、自分の健康を長期に渡って確保することが最重要である。
また、自己犠牲をすることが愛情表現であると捉える人が多いのを知っているが、ひとまず、私はその有効性を否定したい。
その理由は、
特に一般に子育て能力を有する女性と違い、男性は長期の看病は社会的にも生物的にも負担である。サポート体制を十二分に整えねばならない。
確固とした自己愛に基づいた献身。看病の理想である。
相手の話には、ただ耳を傾けるしかない。これは鉄則である。
往々にして相手の意見に反論したり評価したくなるものだが、これはいけない。相手の話は病気が言わせている面もあるのであり、そうした話に対して理路整然と反論したり、感情的に非難すると相手は混乱してしまい、何もいいことはない。
ひたすら耳を傾け、相手の運命への呪いや周囲への不満を聴き届け、共に相手の不遇を悲しみ、相手に落ち度がないと繰り返し伝えることである。患者の苦しみを思えば、その怒りや呪いすら正当であると静かに認めてあげよう。
看病に雄弁は禁物である。
時に相手は自分を責めてくるものである。これにも基本は相手の落ち度がないことを認める方針を崩さないことが大切である。
その為にも、責められたら即座に詫びることである。それ以外は全て言い訳であり、どんなに自分が努力したにしても、苦しんでいる人がいる以上、詫びても罰は当たらないだろう。
また、同様に相手は自分の努力で責めてくるかもしれない。そうならば素直に感謝すればよい。
とにかく非難したり反論しても得は何もない。相手を認めてあげよう。
言うまでもないが、鬱病患者を激励したり、責めるのは百害あって一利なしである。その程度で行動が変化するなら病気ではないのであり、事態をややこしくするだけである。
勿論「お前はそんな性格だから、そんな病気になるんだ!」と怒鳴りたい瞬間もあるかと思う。しかし、それは医学的には証明されておらず、不毛で無益な主張であり、事態を悪化させるだけである。
基本は、相手に落ち度がないのに、理不尽に不幸に見舞われていることを、共に悲しむことである。そして、自然治癒力によって脳が治ることを共に待つことである。
誠に人にできることは待つことだけであり、苦しむ人の側に居てあげることだけである。
ともすると病気であることを相手も自分も忘れてしまうものである。あるいは、当初はこうした病気は認めずらいものである。
しかし、病気である現状を認めないことには、治療は始まらない。自分も相手も納得した上で薬を飲み、ストレスをなくした環境で静養する必要がある。
得に「あせり」「無能感」「怠惰への恐怖」などに対しては病気の認知をすることで対応するしかない。ストレスなく静かに静養できない場合は、鬱病の勉強が救いになることもある。
苦しむ人と接するには H.S.クシュナー『なぜ私だけが苦しむのか』 が参考になる。是非、一読して欲しい。
鬱病への誤解が多く、鬱病の人は更に苦しむことになる。鬱病は心の病気じゃないし、甘えているわけじゃない。誰でもなる可能性のある病気であり、治る病気だ。典型的な誤解を7つリストアップしてみた。
違う。鬱病とは身体的な病気であって、その症状の一部として精神的、心理的に現われたものと考えて欲しい。
違う。身体的な原因により、本人の意志ではどうにもならない状況が鬱病である。
鬱病の人が愚痴や文句を言うのは、インフルエンザの人が熱を出したり鼻水を出したりするのと同じだと考えて欲しい。
違う。持てる能力をフルに発揮できていないにしても、中程度の症状なら、どうにか話したり仕事したりできる。だから、普通に話しせるんだから病気じゃないというのは違う。
違う。そもそも、そうしたポジティブな思考をしたり、過去を忘れたりする機能に問題が生じているのだと考えて欲しい。繰り返すが意志でコントロールできるなら病気ではない。
鬱病の人が頑張って前向きに生きようとしたり、過去を忘れようと努力しても、うまくいく可能性は低い。逆に自分が弱いのだと誤解したり、罪の意識や恥の意識に苦しんでしまい、治りにくくなるかもしれない。
違う。鬱病はその人の感情を蝕むだけでなく、健康も、人間関係も、仕事も、思考力も奪ってゆく深刻な病気である。ときには命さえも奪う恐しい病気だ。自殺率は10%を超えるとも言われる。
また沈み込む症状ではない鬱病もあり、中でも攻撃的になる激越性の場合には自殺は50%を超えるともいわれる。
違う。適切に処置すれば多くの場合は治る。少なくとも改善に向かう。治療方針は基本的には一般の病気と同じで、自分と周囲が病気であることを正確に認知し、薬を飲み、養生して、回復を待つことである。身体の病気であるので身体の治癒力に頼るのである。
違う。鬱病の原因に定説はないが、基本的には社会的・生物的ストレスと遺伝的、生理的なものが原因であると考えられており、個人の性格や能力などに関係があるのは証明されていない。その意味で、誰でもかかる可能性がある病気である。癌になる人が特別な人とは言えないのと同じである。
生涯の間に鬱病になる人は男性で12%、女性で20-25%にのぼる。この数値は上昇すると考えられており、WHOの予測では、2020年には世界全体で仕事ができなくなる原因の第1位となるとされている。
社会的費用を軽減するためにも、幅広い理解が必要な病気であると言えるだろう。
ようするに問題オリエンティッドに知識を再編成する=お勉強だったりするわけですよ。とのこと。 以前にノート の取り方にてコーネル大学式のノートの取り方とかもメモしたけど、結構、問題集を作成するってのはお勉強には有効なんだろう。というのは、目標が問題を解くことなんだから、それに特化した勉強法、ノート作成法が有益だろう。目標がボケると成果もボケるものだ。
もし、成人が社会全体の利益を考えずに、自分の利益のみに基づいて行動した場合、社会は破綻する。この社会を支えるのが大人なのだという理屈。
でも、この「成人=社会費用最小努力者」説は、要は「人のために尽せ」という精神論みたいになる。まあ、そういう解釈もありえるかなとか。だから、私は、この説を人様には言わないことにしている(いや、昔は行ったゴメン)。というのは、「人のためにつくせよ」ということは「俺のためにしろよ」ということであり、「じゃあ、テメーがすれば?」という批判に晒されるのは必至だからである。
かくして、私はモラルは人には伝えられない、と思っている。モラルを強制するのは暴力である。私は他人に暴力を使えない。ただ、「でもね、そうしないとね、社会がね……」と内心思いながら「まあ、仕方ねえなあ」とか思う次第である。一人で勝手にやってるしかない。
教育とは、こうしたモラル、社会を成立させるモラルを植えつける暴力であるのだと思うのだが、どうも最近は、そうしたモラルは古臭いようである。そして家族も学校も会社も地域も、いかなる社会も破綻に向かっていると感じる。
まあ、それこそ、誇大妄想もいいとこだが……。ってのは、昔から人間ってのは自分勝手に生きてきて、それで、そこそこうまくやってきたんだろうとは思うんだけどね。現代と比べても庶民が昔から「自分勝手」であることは歴史が教えるところだ。
ま、私は一人で勝手に損をしながら、抽象的で偽善的な「モラル」を生きてゆくのだろうとか。
地上デジタル放送対応のチューナー(録画機能などを含まないチューナー単体の市場実売価格:2~10万円程度)、あるいは同対応のテレビ受像機ないしHDDレコーダー(ネット通販で最安で5万円台で販売されている例もあり、チューナー単体を買うより割安と言える。ただし、起動に時間が掛かる機種が多いのが難点)が必要となる。 (……) 現在、単体のチューナーを生産しているのはソニー、松下電器産業、シャープ、DXアンテナ、マスプロ電工、ユニデン、アイ・オー・データ機器の7社のみで、OEM製品を含めても種類は少ない。なお、ユニデンのモデル(八木アンテナ・AVOXにOEMあり)は地上デジタル専用で、データ放送と双方向機能に加えてEPGも搭載していない(番組情報の表示は可能)。また、マスプロ電工のモデルはHDMI出力や光デジタル音声出力を搭載していないため、5.1サラウンドはできない。とのこと。大変そうだ。
最近、脳の本を読んでいると実に内容が哲学的なのに驚く。一昔前の脳の実体論的・万能論な常識は完全に通用しなくなっていることが分かる。また、世界の認識についても素朴な実在論は通用しないことも脳の科学が示してくれている。
別に脳の科学で全部を語れるとも、語るべきとも思わないが、脳科学の進歩に注意を払うのは、現代人でちょっと物を考える人には必要不可欠だろう。
今回は、そうした脳の科学が訴える「常識」の変革を少々。
従来、脳と体の関係ってのは脳から体への一方通行の指令で、体をスポッと変えても脳の機能は変わらないとか考えられてきた。つまり、例えば脳みそを取り出して違う身体に移植したりできるんじゃないか、と。SFでよくあるパターン。
しかし、最近は、体が脳を決めている部分があることにも注目しなきゃいけないことが分かってきたんだ。つまり身体のあり方が脳のあり方を規定しているということ。だから、身体が変化したら脳の構造も変化しちゃうんだ。例えば指が四本しかない人は、四本に対応するだけしか脳の分化がなく、また、その人の指を手術で五本にしたら、なんと一週間足らずで脳の対応もきちんと五本のために分化するんだ。おそらく、私たちの指が六本になったら、脳も早急にそれに対応するだろうね。脳と身体はまさに一心同体なんだ。
よく私たちは脳の全体の数パーセントしか使ってないっていうよね? それくらいに脳というのは高機能で、どちらかというと私たちの身体の方がそれに追いついていないくらいなんだ。
脳に機能的余裕があるからこそ、私たちは自らの身体を使いこなすことを超え、道具を「手足のように」使いこなしたりできるんだろうと私は考える。事実、サルが道具を使っているときには、道具の先端を操作するときに、素手の時には指先の部分で反応していた神経が活動しているらしい。スポーツや楽器の演奏をする身体は高機能な脳に支えられているんだね。そしてその時、脳も変化しているんだ。
今、身体と脳の関係が普通に考えられているのは違うって言ったけど、実は世界と私たちの認識の関係も考え直す必要があるかもしれない。
私たちにとって「世界」とは脳が理解した世界なわけだよね。でも、脳が外部から取り入れている情報というのは実は完全なものじゃない。視神経で考えたって100万本しかないから100万画素しか取り込めないし、その情報すら脳内のほかの情報の影響を強く受けるんだ。
そして考えて欲しいんだけど、100万画素の画像はかなり荒い。でも私たちが見ている世界は「荒く」なんてないよね。つまり、かなり荒い情報しか入力していないのに荒くない映像が「見えている」ということは、脳が補完をして映像を作り出しているということなんだ。
するとどうだろう。自分が見えている世界が、実際にその通りにあることが疑わしく思うんじゃないかな。
こうして考えていると、本ブルグでも触れた『脳と仮想』や『進化しすぎた脳』などを読んでみて、科学としての脳の研究の将来を考えたくなるかもしれない。
また一方で、素朴実在論という常識を離れてゆき、哲学や宗教などに興味が湧くかもしれない。宗教なら本ブログでも取り上げた『道元 - 自己・時間・世界はどのように成立するか』で日本最高の知性の一人の道元の思想に触れたり、『インテグラル・ヨーガ - パタンジャリのヨーガ・スートラ』でヨーガ思想を垣間見るのもよいかもしれない。同様に仏教の他の思想、例えば中観や唯識にも興味が湧くかもしれない。
スワミ・ヨーゲシヴァラナンダ『魂の科学』を読んでみた。本書は五つの鞘の解説書であり、三年ほどでの修行スケジュールをフォーカスしているのだが、師の体験談には、師は以下のプログラムによって一カ月でかなりのレベル(空虚三昧に入る)にいったとある。
参考にメモ。
食事は一日一度、米とバターと塩のみ。
こうしたヨーガの集中トレーニングをいつかしてみたいものだ。
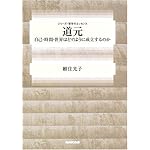
コンパクトな道元入門書。分かりやすいが奥が深い。空と悟り、時間・存在論を総合的に解説。
ハイデガー『存在と時間』は道元『正法眼蔵』の影響?から、道元の「有時」 - 「いまここ」の場と書いてきて、ちょっと道元の入門書でも読みたくなった。
小さな本がよかったので、試しにシリーズ・哲学のエッセンスの『道元 - 自己・時間・世界はどのように成立するのか』を読んでみた。全体として分かりやすく、とてもコンパクトに道元思想を解説してくれているように思う。原文の引用の後に必ず現代語訳がつき、最後に文献紹介がついているのも有難い。
著者についてはお茶の水女子大学の教育研究者情報によれば
日本思想における超越観念の諸様態を解明が研究課題で、具体的には 1)道元、空海、親鸞等の古代中世の主要な仏教思想家、とくに道元の主著『正法眼蔵』の注釈と思想構造の解明、 2)仏教説話等をてがかりに、日本人の精神世界の形成に仏教が果した役割についての考察、 3)和辻哲郎、西田幾多郎、宮沢賢治等、近代日本の思想を通じ、世俗化が進んだといわれる近現代における超越性のありようについての検討。とある。また、NHKの高校講座 現代社会の講師もしているようであり、同サイトで声も聞ける。
本書の道元思想解釈がどれほど一般的なのか、妥当性があるのはを私は知らない。ただ、読んで深みのある内容であると感じた。
本書における道元思想は以下のようになるだろう。まず、世界の本当のあり方は「無自性—空—縁起」であり、それを体得することが「解脱」であると説明する。つまり、時間や因果などによる分節・固定・実体化を離れることが「解脱」である。ちなみに、この「無自性—空—縁起」の解釈は、井筒俊彦の意識と本質に関する分節─無分節理論の影響がかなり大きいように思えた。
そして、その無差別・無時間・無意味なカオスから、自己・世界・時間を「われの尽力」によって関係付けて「現成」させることも忘れてはならない。これも「さとり」の一方向と言えるとのこと。
道元によれば、自己も時間も世界も、その根底にあるのは空であった。道元において、「空」とは、「空そのもの」と、相互相依する「空―縁起」として把握される。「さとり」とは、無時間、無意味、「無差別」である「空そのもの」へと還帰し、さらに時間や意味を「現成」させること、すなわち、「空そのもの」から、「空―縁起」なる全体世界を立ち上がらせることであった。(……)「空そのもの」から、自己が世界を「時」として意味付け、自己と関係付けて、「空―縁起」なる全体世界を現成させる。まさに、これこそが、自己と時間と世界との成立なのである。
以上のように、空、解脱、悟りという概念が、現成、有時という存在論、時間論として説明されている。
図も付いていて、説明も図式化されているので全体的な理解をしやすい。仏教用語を知らなくても、道元の思想の全体像を理解できるおすすめの本である。
私にとって興味深かったのは、自己と時間と世界との関係である。以下、本書の説明を下敷にして、自分の解釈に基づき考えてみたい。
繰り返しになるが、本来、空である世界はカオスである。そこでは何も存在はしない。
そこから、存在するためには言語化・意味化が必要であり、それを現成と呼ぶ。存在とは自己によって意味付けられてはじめて存在となるのである。ただし、それは今ここにおいてのみ成立する。物事は本来は空であり、その空であることに基いたまま、自己に基づいて主客合一のまま、今ここにおいて存在する、現成するのである。
空のままでよいではないかと思うかもしれない。しかし、それでは生きてはゆけないし、何よりも、何よりも現成とは普段からしていることであり、その最もシンプルで迷いから離れた世界の存在の仕方なのであるかと思う。
というのは、普段は現成した上に、執着、固定化がついてまわる。現成のみの場合はそうしたものから自由である。私と世界の分離のない今ここにおいてのみ、存在があるのであり、私も存在するのである。それ以外には空のみである。
こうしたことが「本無華といえども今有花」という言葉に示されているかと思う。
そして、そうした現成を体得しているとき、迷いなく生きていると言えるのだろう。
もう少し現成を詳しく考える。この問題は時の問題でもある。本書には、
現成とは空に立脚しつつ、自己に関係付けて「時」化することである。とある。この関係付けることを「配列」と呼ぶ。
そのままでは流れ去り断片化し無意味なものとなってしまうものを、「配列」し、相互に関係付けて意味を与えるということが「時」化することなのである。また、配列としての世界を縁起の世界と同値とも読めるか。
「空」に立脚した「縁起」の世界であり、「無差別」に根ざしつつ、「差別」的事物事象が「現成」する。すべてのものが、他のすべてのものと関係しあいながら一つの全体世界をかたちづくっているととらえられる。この時というのは、有時であり、時があることまさにそのことであり、有の時である。そして、そうしたことを知る自己もあるということである。存在させているのは、とりもなおさず、そうした「見る」自己であり、自己は時に存在させるという仕方でのみ存在する。つまり、見られる対象としての存在と、見る「自己」とが、ある時において成立する。
自己が配列するのであるから、存在は自己が生んだものである。ただし、自己は対象化されない。見ることしかできない。それも純粋に見ることを考えれば分かるように、今ここにおいてしか見ることはできない。自己の配列、自己の見ることを対象化できない。ただ自己はある時において見るのみであり、見られることはない。そうして世界は自己によって現成させられている。本来は空であり、無である。時においてのみ、有があるとは、そうしたことか。
本来、時間も空間も、世界も自己も空である。ただ、今ここにおいてのみ、見る私と見られる世界がある。何もないはずなのに、今ここでは、あるのである。不思議であるが、これを疑うことは難しい。この問題を見極めたいと私は思っている。ただ、分からない。
ただ、ふと思う。これが生きるということかと。
そして、それが生きるということだとすると、つまり、カオスであり空である世界を、その時、その時に見ている自己によって「存在」させるのが生きるということだとすると、生きるとは、流転のカオスの中に、今ここにおいて自己と世界とが存在と時間をすることか。
そのカオスを知覚し、その知覚によって世界と自己を有時/現成させ、更にその他己/有時を知覚し、更に他己を現成する。この空からの「いまここ」という刹那における無限、永遠のプロセスが生きることか。
だとしたら、生きるということは、為すすべもなく、必死に今ここに打ち込みながら、かつ、その今ここをただ見ているだけということか。
居間に転がっていたWIN2K機が不要になり、私の部屋にやって来た。どうせ二台あるなら、ディスプレイを二台並べて、あたかも一台のコンピュータのように使えないだろうか。Dual Headにするためにグラフィックボードを買ったり、設定するのが面倒だと思っていた。
調べてみると便利なソフトが見つかった。synergyだ。使ってみると便利で軽く興奮した。これでWindowsとLinuxがあたかも一台のPCのように使える。
synergyを使うと1セットのキーボードとマウスで二台のパソコンが使える。入力インターフェースが一つなので、感覚としてはディスプレイが2つついた一台のマシンを使っている感じである。クリップボードも共有できる。
勿論、一台のマシンの上でもう片方のOSを coLinux なり VMWare なりのエミュレータで動かして、Dual Head/Twin Viewなグラフィック・カードで使えば同じようなことになる。ただ、ぼんやりと2台のマシンがあって簡単に接続できる場合ならとても手軽な解決法となるはずだ。
まず必要なソフトを公式サイトから落とす。WINには.exe形式のインストーラがあるし、Linux向けにはRPMもある。ちなみにGentoo Linuxではemerge synergyでインストールできた。
次に設定。まず、「サーバ」と「クライアント」が混乱しやすいので以下のように理解して欲しい。
次にクライアント機では、サーバのホスト名を指定する。WINではGUIで設定できるし、UNIXでは
synergyc --daemon <サーバのホスト名>と入力すればいい。
一方、サーバ機の設定では、WINではGUIにて接続するマシンのホスト名を全部入力すし、更にマウスの移動についての設定を行う。
UNIXでは設定ファイルを作る。だいたい以下のようなものだ。
section: screens
dog:
cat:
end
section: links
dog:
right = cat
cat:
left = dog
end
上の例では、dogとcatというホスト名のマシンを登録し、dog機とcat機のディスプレイが右→左と並んでいることを想定している。
あとは、作成した設定ファイルを指定してサーバを起動すればいい。
synergys --daemon --config <設定ファイル>だ。
ただの愚痴である。
今日は月曜、嵐の月曜日である。
朝食を摂りに居間にゆくと、父がドンパチ系の映画を見ている。私は卵焼きと海苔で朝食を済ますのだが、それは断末魔の叫びや銃弾の音の嵐の中でのことになる。まあ「あはーん」「うふーん」な音でないだけマシか。
母も父がいると不機嫌であり、無言で掃除をしている。ええ、掃除をするんですよ、人の食事中。
セカセカとホウキで床を掃き、モップで掃き、食べてるテーブルをフキンで拭く。また、食べ終わったそばから、ガチャガチャ皿を片付ける。そもそも健康サンダルみたいなスリッパを履いているので、動くだけで足音がうるさい。
食事中にホウキで掃かれるのは嫌である。ホコリが舞うのが嫌なのか、ホウキと床が擦れる音が嫌なのかは分からない。たぶん両方であろう。
いや、まったく。愚痴を書いてすまなかったです。
皆様も人の食事中には人が死ぬような映画の音は小さくして、掃除はやめましょう。
ではまた。
私は本を読むのが早い方と思う。人にも言われるし、自分でもなんとなく思っていた。今回はその方法を書く。
その前に今の速度を申告する。昨日、240頁の単行本を読んでみて、ふと読み終わって時間を見たら30分もかかっていなかった。内容は気功関係であり、内容は割に濃いめであったと思う。ただ比較対象が新書などと比べての話であり(新書は5-10分で読める)、学術的、文学的、哲学的な書物と比べての話ではない。
「なるほど、テレビを30分見てる間に一冊本を読めるのか」と、なんとなく思った。これが今の私の標準なのだと思う。普通の人よりは早いだろうが、職業的に読書している人や「速読」の人と比べると遅いと思う。ちなみに、私の信頼できる友人がこの速度より遅いとは思えない。
私は一日一時間半前後は読書にあてていると思うので、なんとなく2、3冊は読んでる。中には昔から読んでいる小説や哲学書をパーっと読むこともある(そういえば、最近は新規で分厚い哲学書や小説に手を出さなくなった)。
以上が大体の私の読書の量と速度である。人に偉そうに書くほどではないが、まあ少しは早い方だというのがご理解いただけたかと思う。だから、私よりも既に早い人にはあまり参考にならないかと思う。
「テレビは時間あたりの情報量が少ないから本を読もう」などと言う人がいるが、それは人によるとしか言えない。一冊に何時間も掛かるようならテレビを見た方が効率が良いと思う。事実、よくできたドキュメンタリーの時間あたりの情報量は通常の本よりも確実に大きい。それに映像や音声は書籍では触れられない。いつも思うのだが、読むのが遅い人が読書を礼賛しても、なんの意味もない。
「速く読むのもいいが、それじゃあ文章を味わえない」と思うかもしれない。それなら漱石や芥川、鴎外が大量な書物を素早く読んでいたことをどう考えるべきか。そもそも、一定量の読書がなければ、文章を味わうもなにもないと思う。それに速く読めるようになっても、遅く読むことは出来るのである。
若い人は早いうちに、早く大量に本を読むコツを身に付けて欲しいと思う。
まず、誰にでもすすめられる速読練習法である。
一度読んだ本を二度目に読めば、当然早く読み終わる。三度目には頁の印象すら覚えているかもしれない。四度目には頁を見ただけで、内容があちらからやって来るだろう。
こうして何度も読んでいくと、最終的にはパラパラとめくるだけで、本を通読することができるようになる。
「そりゃ、何度も読めば内容を覚えているんだから、パラパラめくるだけで通読した気になるのは当然だ」と思うかもしれない。
しかし、考えて欲しい。いや頭で考えるのでなく、心で感じて欲しい。「なぜ、頁を見ただけで、内容が飛びこんでくるのだろうか?」いったい、その時、何が頭の中で起きているのかと。これが、初めての本でもできるようになれば、かなりの速度で本が読めるようになる筈である。
文字を追わないでも、ただ頁を見るだけで内容が飛び込んで来ることが出来ることを確認して欲しい。それは記憶に補助されているが、それだけではない。どこかで意識の底で頁の内容を把握している筈である。ならば、その意識の底の把握能力だけで「ああ、この頁はこんなこと書いてあるな」と感じるようになれば、かなりの速度で読める筈である。
繰り返し読むことによる高速化は、速読体験の基礎となると思う。是非、お気に入りの本を何度も読んでみて、その感覚の変化を吟味して欲しい。
速読をしようと思っても、読む量が人並ならば、速度も向上しない。必要に迫られて能力は開花する。ならば、少し無理そうな冊数を一日のノルマにして、ガバーと読むようにすると、適度なストレスがかかり、速読を体が覚えてくる。
具体的には、一時的にでもいいから一日10冊以上は読書すべきかと思う。それくらいの量の読書をしようと思うと、読書の方法も変わってしまうし、質も変わってしまう。ただ、理解も関係なく、頁をめくり続けていればよい。どちらかと言うと、文字をきちんと追うよりも、ぼんやりと頁を見ながらめくるとよい。頁を見て内容を知覚する直感能力、勘を養っているのだ。
また、多量の読書が与える知識が、他の本を読む速度を向上させるだろう。
これも私が無意識にやっていた読書練習法。
私は生まれ付きひねくれているので、たまに本を後の頁から読んだ。最初は意味不明にしかならないかったのだが、ある日、何度も読んで、頁を見るだけで内容が飛び込むようになっていた小説を後の頁から眺めてゆくと、意味が分かることに気がついた。小説を後から読んでも、きちんと時間が逆に流れる小説になったのである。面白くて一人でとても興奮した。
また、小説でなくとも、普通の本でも後から読める。前提→事実→結論というような流れの文章は、結論→事実→前提と読んでいっても理解はできる。「雨が降ったから、家で寝ていた」が「家で寝ていた。雨が降ったから」でも理解できるのと同じである。
更にひねくれている私は、ちょっとした文書なら逆からでも読める。文ごとに視野に入れて、内容を把握し、文書の論理・時間構造を逆にたどるのである。
この遊びの何がよいかと言うと、文字をきちんと追わないと意味が把握できないという偏見を脱却するためである。「桃太郎は旅立ち、仲間と出会い、鬼を倒した」という文章は「鬼は桃太郎によって倒された、その前には仲間を集めがあり、その前には旅立ちの日があった」という風にも読めるのである。
こうした感覚を養うと、読書が「文字を追う」から違った次元になってきて、かなり速くなると思う。
読むのが遅い人は本を一つの塊として見ていない。延々と続く文字の羅列である。
この状態を脱却するには、目次を利用するのがよい。目次を眺めれば、本の凡その枠組みは理解できる。そうならば、目次を眺めて内容を予想してみて、その後で本文を読んで予想と実際がどの程度違ったかを考えるようにすると、本を一つの塊として認識するようになる。
そのためには、本を読む前に、目次を暗記するとよい。目次に知らない単語があれば調べておく(本文を見る)。そうして目次を暗記してから、頭の中で本の全体像を思い描くのである。
読書後には再び目次を見て、当初の印象とどのように変わったかを吟味するのである。
本当は友人にどういう本だったかを語ると良いのだが、なかなか難しい。そこで、一人でぼんやりと空でも見ながら本の内容を想起するのである。出来ることなら、頁の映像を思い出し、更には何個かの文章も思い出してみるとよい。
ただ全体としては細部にこだわらず、どういう枠組みの本だったかを思い浮かべられればよい。その点でも目次の暗記は役に立つだろう。
別にいつものノリで書くわけじゃない。結局、読書の一番のロスは固定した悪い姿勢で疲れてしまうことなのだ。
一冊に30分かかるなら、30分は姿勢を保持しなければならない。2時間なら2時間、姿勢を保持しなければならない。ただ、普通は姿勢を保持できない。机からソファー、ソファーからベッド、ベッドから夢の中へと読書空間は移動し、多大なロスが生じる。気を抜くのだから、確実に読書の集中は奪われ、速度は落ちる。
そこで、最初からよい姿勢に気をつけるのがよい。結局は背筋を伸ばして、顎を引いて、頭頂を床にぶっさすように坐ることである。勿論、書見台も利用したい。
そこで固定した姿勢で集中できれば、かなり時間の面でも精神面でもロスが少なくなる。
坐って姿勢を決めたら「よし、読了までは動かないぞ」と肚を決めて読書に望むのもよいと思う。読書坐禅である。そのうち「悟るまでは動かないぞ」と言って瞑想し出すのもよいかもしれない。
以上のことを私は速読の練習というより、遊びとしてやって来た。やってみると楽しいものであり、読書の方法が変わり速度が速くなる。よろしければ試してみてもらい、感想を教えて欲しい。
ただ、結局、一番の速読を身に付ける方法は、大量に読まなければならない状況に身を置くことだろう。職業だけでなくとも、学生ならば旺盛な知識欲が読書能力に刺激を加えるだろう。人間の必要に追われての適応能力は高く、また堕落の適応力も高いのである。
仏教とヨーガの関係を整理。豊かな宗教を取り戻すために。
実は本書は以前も取り上げた本だが(2007/01/09仏教関係の読書記録)また取り上げることにする。ヨーガや仏教の理解がこの半年で深まったせいもあり、本書のように全体を大きく眺めるような本を再び読みたくなったからだ。
ヨーガと仏教というと、どういうイメージだろうか。ヨーガは怪しいイメージかもしれないし、逆にホットヨガのように若い女性のものというイメージかもしれない。仏教は葬式の道具というのが一般的か。あるいは、その両方に対し、オウム真理教などの過激な新興宗教を連想する方もいるかもしれない。
本書では、そうした現代の「宗教」観を問い直し、現代の日本人の心身を救う正しい宗教のイメージを考える。そのキーワードとなるのが、ヨーガと仏教なのである。
目次は以下の通りである。
序 仏教ヨーガの提唱
第1章 「宗教」と宗教観
第2章 ヨーガの諸相
第3章 インドにおけるヨーガの歴史
第4章 ゴータマ・ブッダとヨーガ
第5章 『ヨーガ・スートラ』の教え
第6章 仏教の展開とヨーガ
第7章 日本におけるヨーガ
まず、筆者はインドにおいてヨーガが瞑想法として、いかに重要な役割を担っていたのかを説明する。仏教も、ヒンドゥー教も、それどころかイスラム教のスーフィズムもヨーガの影響なしには、現在の形ではないとのことである。この視点で考えると、坐禅はヨーガの一種である。
また、一方で、仏教の知恵もヨーガの成立に強い影響を与えたことも述べられてゆく。そうして、ヨーガと仏教が混然と日本の文化に入っていることを明らかにする。ヨーガと仏教は切り離すことはできないのである。
そこで考えられるのは、ヨーガの修行と仏教の知恵を組み合わせてゆくということだろう。これが、著者の主張する、心身の本当の健康の道である。
特に興味をひいたのは、ヨーガ・スートラの考証であり、その中で仏教の影響の部分などを分析してあったことである。ヨーガ・スートラの「ヨーガは心の作用の止滅である」などの部分は、初期仏教の強い影響からと説いた部分であり、逆に最終章では唯識に対する反論もあるとのこと。ヨーガ学派は、仏教と極めて近い場所にいたことがわかる。
また、外部から見ていたヨーガ学派のヨーガ・スートラを読むことで、初期仏教(原始仏教)から瑜伽行唯識派という仏教の発展も読み取れる。以前にも感じていた仏教とヨーガの関係の疑問(『インテグラル・ヨーガ - パタンジャリのヨーガ・スートラ』の書評を参照)も、整理できた感じだ。
本書を読むとヨーガが実に歴史が長く、その原理も実践方法も多様であることが分かる(先日の『ヨーガ・セラピー』はハタヨーガに基づいた心身の健康法と言える)。そして、その修行法なくして仏教の智慧がなかったことも考えると、仏教を考える上でもしっかりと学びたい分野である。
著者はオウム真理教の一連の事件をしっかりと受け止め、現代日本人にとっての本当の宗教を考えている。宗教などに嫌悪を感じる人も、是非一度は眺めてみて欲しい。
インド政府厚生省の要望で書かれたヨーガ療法の教科書。ヨーガ療法に興味がある人は必読と思う。
本書を見掛けたのは図書館だった。ヨーガ・セラピーというタイトルといい、黄色のポップな表紙といい、若い女性向けに書かれたちょっとオシャレな内容の薄い本であろうと思い、しばらく手に取らないでいた。
偏見であった。本書は信頼できるヨーガ療法に関する教科書であった。なんと言ってもインド政府の要望によって特別に書かれた本である。更に推薦文を文化勲章受賞のインド学、仏教学の権威、中村元博士も寄せていることから、ますます信頼度は高いと言える。
中村によれば、著者のクヴァラヤーナンダはインドの伝統的な学問を充分に究めたヨーギであり、その上、近代科学の計器による測定・検討も行っている。「クヴァラヤーナンダ師が創立したヨーガ研究所 カイヴァルヤダーマは、世界諸国のヨーガ研究者たちのいわばメッカとなっている」。
また木村慧心によれば、1920年代に創設されたカイヴァルヤダーマ・ヨーガ研究所は、医学研究所や病院、ヨーガ大学、図書館等の施設を伴なった世界で初めてのヨーガ・セラピーの研究施設であり、この分野をリードしてきたとのことである。
内容は以下の目次の通りであり、特に精神や神経の疾患に対してのヨーガ・セラピーの原理と実践を医学的な誠実さを伴なって丁寧に説明してくれる。その中に迷信じみた説明は見られない。
第1章 ヨーガの病気観とヨーガ・セラピーの原理
第2章 正しい心の姿勢を培う
第3章 精神生理的メカニズムの再調整
第4章 身体浄化法、食事の原則
第5章 瞑想—すばらしい精神安定法
第6章 ヨーガ・セラピーの実践
特に興味をひいたのは、何故、ヨーガが心の安定を生むのに役立つかを、大脳や神経、筋肉などの医学的な説明で極めて丁寧に説明してあったことである。その説明の中で、ヨーガをリラックスした状態で静かにやらねばならないことが理解できた。「アーサナの生理的効果は、運動の生理学である運動学の原理にもとづくのではなく、姿勢の特徴である静的緊張反射の原理にもとづいて考えなければな」らないのである。ここにヨーガがストレッチやエアロビクスと一線を画す本質があるのかと思う。勿論、呼吸や瞑想の説明も素晴しいが、アーサナに関するこの部分だけでも必読の説明である。
また、説明の誠実さだけでなく、視野の広さも素晴らしい。本書は、アーサナ(坐法)や調気法(呼吸法)、瞑想法などの一般的なヨーガのテクニックの他に、一般にはあまり知られていないであろう鼻や喉などの呼吸器や内蔵を清浄化するヨーガのテクニックも掲載している(以前にハタ・ヨーガ・プラディーピカーを読んだ際に目には入っていた)。勿論、実際に行う際には専門家に相談すべきだが、ヨーガ・セラピーの幅広さを感じられるだろう。
ヨーガの書籍は沢山ある。勿論、伝統の人の本を読むのもよいが、まずは近代科学の検討を経て整理・解釈された伝統の教えを、本書で知るのがよいと思う。

「神がいるというのに、なぜ善良な人々に悪いことが起きるのか?」 この本はこの問いへの答えを語り抜いた本である。
しかし、これは哲学的な議論であったり神学的な議論ではない。成人前には死んでしまう難病の息子を持った一人の父親が、それでもいかにして世界を受けいれていったのかを綴ったものである。
「どうして、この私にこんなことが起こるのだ? 私がいったい、どんなことをしたというのか?」本書は苦しむ人はもちろん、苦しむ人と接する人にとっても重要な指摘に満ちている。是非、手にとってみて欲しい。
学者や僧侶、一般人が言いそうなことは、全て否定されていると言ってよいと思う。いかにも不幸な人に言いそうなことが、なぜ言うべきでも考えるべきでもないかが説明されている。本書を読みつつ反省すると、多くの人に何度も間違ったことを話したものだと心苦しくなる。
それでは、どうしたらいいのか? それは本書を繙いて頂きたい。が、簡単に言えば、ただ共にいて黙って話を聞いてあげること。苦しむ人がなんの罪もなく、何の言われもなく不条理に不幸に見舞われていることを認めてあげてあげること。時には、そうした不条理な状況そのものに共に苦しみ、時には共に怒りを燃やすこと。そして、苦しむ人に「あなたは孤独ではない」と伝えるということだ。
そうしたことを通じて、自然に「すでに、こうなってしまった今、私はどうすればいいのか?」と未来に目が向かうようにすればいい。不幸な人に下手な議論をしてもしかたがないのだから。
しかし、これは単純なことではない。私は本書を時間をかけてゆっくりと読んだ。
例えば以下に著者の心情が表れているが、こうした著者の感性を読みながら、彼の思索を辿ることは経験の浅い私にはかなりの内省を必要としたのである。
アーロン[著者の息子の名前]の生と死を経験した今、私は以前より感受性の豊かな人間になったし、人の役に立つ司牧者になったし、思いやりのあるカウンセラーにもなったと思います。でも、もし息子が生き返って私の所に帰ってこれるのなら、そんなものはすべて一瞬のうちに捨ててしまうことでしょう。もし選べるものなら、息子の死の体験によってもたらされた精神的な成長や深さなどいらないから、十五年前に戻って、人を助けたり助けられなかったりのありきたりのラビ、平凡なカウンセラーとして、聡明で元気のいい男の子の父親でいられたら、どんなにいいだろうかと思います。しかし、そのような選択はできないのです。
平凡を願う人はなんとも哀しい。
 や低農薬野菜や無添加食品の宅配サービスである。
や低農薬野菜や無添加食品の宅配サービスである。 や低農薬野菜や無添加食品の宅配サービスである。大規模で画一的な流通ではない。見てもらえば分かるが、個別的でなかなかに個性的な品揃え(年間約4,000アイテムの豊富な品揃え)である。
や低農薬野菜や無添加食品の宅配サービスである。大規模で画一的な流通ではない。見てもらえば分かるが、個別的でなかなかに個性的な品揃え(年間約4,000アイテムの豊富な品揃え)である。「なぜ?」と問われた時に、「分からない」と答えるのは難しい。
「なぜ私の胃はこんなに痛いのか?」と問われれば、色々な理屈を持ち出してしまう。「昨日たべすぎたんじゃないか」「胃がもともと弱いんじゃないか」と色々と答えてしまう。
まあ胃が痛い程度なら、無責任に答えても問題はない。しかし、「なぜ、こんなことが起きたのか?」「なぜ、こんな悲惨なことが?」「なぜ、こんな苦しいことが?」といったような、本当に相手が不幸なときの問いには、ただ分からないと言うしかない。
その人は傷ついているだけだ。「申し訳ないが、分からない。とても残念なことだ」と言って、相手が何も悪くないことを示してあげて、世界の不条理に共に悲しむことしかできないのだろう。何も上手いことを言う必要はない。黙って耳を傾け隣に居ればよいではないか。
なぜ人は「分からない」と言うかわりに「日頃の心掛け」「先祖の祟り」「前世の因縁」などと、自分にとってすら意味不明の答えをして、人を苦しめてしまうのだろう。
cckjb015 さんの質問への解答をします。失礼かとは思いますが、コメント欄に書くのが狭くて面倒なので……。
「苦行」も捕われれば欲になるのでしょうか。については、ちょっと質問そのものを考えますね。基本的には欲はオーケーと考えます。問題は執着することであり、「とらわれること」そのものが問題と思います。
例えば食欲はあればあったで、苦しくはない欲望です。食べると嬉しいし楽しいです。ただ、それがある種のとらわれになり、執着になると生きずらくなります。「何で食べられないんだ!」とか怒ると苦しいです。とらわれないと楽です。
食べられる時は食べて幸せになって、食べられない時は食べられないなりに幸せになるのがいいと思います。
欲があっても、楽しかったりするのはオーケーです。苦しくないですから。問題は、そうした欲にとらわれて苦しくなったりすることが問題です。人は欲が充足されない事それ自体よりも、時に「とらわれ」によって苦しむものです。
食欲の例で言えば、皆で一二食抜くくらいは普通は大したストレスにはなりません。「カネないねー」とか言いながら友人と寂しい夕食を分けあうのは喜びすらありました。若いから、というだけでなく、人間はその他の動物と基本は同じなので、本来はそれくらいはつらくないように出来ていると思います。多くの宗教などで断食や節食をしていることを考えてもそう思います。
ただ、それが人と比較したりする時に、苦しくなります。「なぜ、食べられないんだ!」となります。とらわれが深ければ、きちんと食事があっても、周りの人がうまそうなものを食べていると自分と比べてしまって苦しいかもしれません。比較はとらわれです。「いま・ここ」で幸せになろうとすればよいので、比較をして苦しくなるのは苦しいです。食のとらわれで、無駄に「おいしいもの」を「大量に」食べて精神や身体を破壊する可能性すらあると思います。それは苦しいです。
苦行をすることも大いに結構です。それが苦しくなければ……というと難しいですが、それがある種の爽快感を与えたりする筈ですから、気持ちいいんじゃないかと思うんです。
ただ、それが執着になり、苦行なしでは生きていけないとなってしまったり、他の人を軽蔑したりしだすとよくないと思います。そういう人生って苦しいですから。苦行は苦行でよいと思うからやっているが(実際よさがあるのでしょう)、やらないならやらないでもオーケーというのが理想かと思います。
何にも捕われない心というのはあり得るのでしょうか。いたらなさのようなものによって、何か気づきながら生きて行くのかなあと思ったりします。
「さとり」をある意味で否定し、ある意味で「修行」し続けて生きてゆくという、 id:cckjb015 さんの言うような考えは、有力な考え方と思います。道元の立場の立場と言えるのではないかと不勉強ながら思います。
一方で超越的な「さとり」を訴える人もいますし、限定的ではあるけれども欲望のコントロールが完全にできるという意味での「さとり」を訴える人もいます。どれも稚拙な文ですが2007/05/29に書いた[書評] 仏教誕生 / 宮元啓一や2007/06/08の私の仏教と禅の理解、それに毛色は違いますが2007/04/19の[書評] タオの気功 - 健康法から仙人への修練まで / 孫俊清などをお読み下されば、参考になるかと存じます。
豊富な「悟り」に向けた体系があること自体、人間がそうしたことを考えるほど豊かで余裕が持てるようになったとも取れますし、逆に、それほどに生きるのがつらいということの現れかとも思います。共に知性を持ったことが原因でしょう。
私がよく出す比喩なのですが、自転車や泳ぎを覚えるようなものと考えております。自転車や水泳は、一度コツをつかめば忘れません。「昨日はできたけど、今日は調子が悪くてちょっと……」ということは特別の事情以外はない筈です。
「悟る」のもそういうことだと思うのです。悟りの定義をここで便宜的にしておきますが、自然にあるがままに、あるべきものごとを愛せてしまうこと、としておきましょう。全ての物事を愛せてしまうので、その人から見れば世界は自由自在な訳です。
ここで注意が必要かもしれませんね。私は超人的な能力を人間が獲得できないという立場です。全てを思いのままにできる人はいないと思います。実在するなら世界は今あるようではないと思います。それにブッダも身体的疾患を抱えて80で死んだ訳ですし、イエスもゴルゴダの丘で「我が神よ、どうして私を見捨てたのですか」と叫んで死んだわけです。
自由自在になっているから、物事を愛せるのではなく、物事を愛してしまうから、自由を感じるのだと考えております。いかなる結果が起きても、それを愛してしまえれば、その人は不自由を感じないのではないかと思います。
しかしながら、問題は、どう考えても理不尽なことが起きた時です。それも自分が殺されるとか拷問されるではなく(それなら愛そうと思えば愛せるのは想像できます)、人が苦痛にもだえ、死ぬ時です。それも無意味に無惨に大量に。理不尽な人の死を愛せるのかという問題があります。実は自分なりの答はあるのですが、誤解しか生まないでしょうから、いま書いたけど消しました。、イエスが「我が神よ、どうして私を見捨てたのですか」と叫んで死んだことを、それでも、なおかつイエスが神の子であったと考えて解釈すると出て来ました(ちなみに詩篇22の引用と考えても悲痛な叫びであることは変わらないと思います。いや、詩篇22を合わせた方が、よっぽど絶望的に思えます)。
そして、そうした悟りの状態になる、悟りの光が現われるように、ある種の人間は出来ていると思います。つまり、苦しみがなく、不自由を感じずに暮らせるように人間は出来ているのだと思います。
そういう人は沢山いたし、いまもいると思います。その人は悟っているとも思わないでしょうし、特別な能力があるわけでもないから、人々も特別視しません。ただ、苦しみや不自由を感じる回路が存在しないで、何でも愛せて生きている人は必ずいるように思えるのです。いや、正確に言えば、私の認識では何人かいるのです。
勿論、ただの勘違いの可能性が高いのですが、私には、そう人間はなれると思えてならないのです。世の中が不完全だと骨の髄まで痛感した人は、苦しみや不自由を感じると思えないのです。別に必ずしも痛い目を見る必要があるわけではありません(勿論、実体験は有効ですが……ただ、ビルから落ちたら死ぬことを実体験で確認する必要がないのと同じく、世の中が不完全であることを実体験で確認する必要は少ないと思います)。ただ、そうした教育や文化があれば、そうした暮らしは可能と思います。
傲慢な物言いですが、あくまで説明のために書きますが、現に私自身の苦痛が減っているのです。なんといいますか、かなり苦しくなく生きられるようになって来ているのです。怒ります、悲しみます、痛がります、腹減ります。でも、とらわれによる苦しみが減っているのです。ある意味で、苦しみが無いと言ってもよいくらいに、苦しくないのです。
状況が良くなったんじゃないかと思われるかもしれません。そんなことはありません。「みじめ」と言ってさしつかえない状況なのです。
慣れただけじゃないかと思われるかもしれません。ただ、そうとは思えないのです。
ただ、執着と呼ぶべきものが離れていったと思うのです。大きなものは虚栄心でした。人に認められたい。理解して欲しい。正しいと言って欲しい。無能に思われたくない。バカと思われたくない……などなどの執着がやっと取れたのです。
そして過去や未来を妄想しなくなったのです。思い出すだけで全身が燃えるような後悔や悔やしさ、絶望的な不安や恐怖から自由になり、目の前の現実を苦しくなく生きることに集中できるようになったのです。
それは、ゆっくりとそうなったというよりは、身に付いたという感覚なのです。
ただ、ここまで読んでご理解いただける通り、私は、この程度のレヴェルなのです。この程度のレベルの人は多くいることは理解しているので、何もこんな文書を長々と書くような人間ではないのです。人によっては生まれた時にクリヤしている問題を、私は二十をだいぶ過ぎてから、やっとのことで、かなりの努力をして、身に付いたというだけなのです(しかし、比較する気もないので、だからどうしたという訳ではありません。私にとっては貴重な成長で、それが何より価値があります。ただ、人様に読ませている以上、私が他の人と比較してどういう状況かを嘘をつかずに報告する義務はあると思いましたので)。
2007/06/03に父の幸福を祈る(1) 過去を変えるにも書いた通り、私はやっとこの歳で、他の多くの人が場合によっては生まれた時からクリアしているような問題を、乗り越えつつあるのです。はっきり言えば、恥ずべきことと存じます。この歳まで、そして今も、父を恨んでいることは、恥ずべきことです。そして、私はいかなる意味でも、その程度の人間なのです。その程度の段階から、少しでも少しでも、そう本当に少しでも、恨みを無くし、苦しみがなく生きてゆけるようになりたいだけの男なのです。
ただ、それでも、そうして恨んだまま、生活をしていき、子をさずかり、その子を苦しませるよりは、ここで、恨みの連鎖を止めたいと思うのです。この「恨みの連鎖」の一文、非常に迷信的ですが、そう思っているのです。
ただ、そうした苦しみが、現実になおったのです。今は胃も頭も腰も何もかも、どこもかしこも、全然痛くないのです。そして、現在も悲惨な生活そのものなのですが、ちっとも苦しくないのです。
そして、何もどこにも苦しいことはないのではないか、不自由はないのではないか、いや、そもそも、私が認識している物事は何も実在していないのではないか、という気分になりました。いや、それは言い過ぎですね。誤解なく言うのは難しいです。
そうした階段を確実に昇ったという実感がある私としては、どうもこの次の階段もありそうで、その次の階段もあり、人間というものは、確実に階段を登れるのではないかと感じているのです。そして、その何段か先に苦しみが完全に発生しないレベルが確実に存在するように思えるのです。
ただ、それは大したことではないのです。世の中には、そうした人が大勢いるのだと思うのです。一方で、人から見たら何でも与えられ幸せに暮らしていそうな人が、本当は生命そのものを呪うほどの苦しみを背負って生きているのです。そうしたものなのだと私は思うのです。
こうした経緯があり、私は超人的なレベルの悟りには懐疑的ですが、ひとまず運命愛とでもいえるような、あるがままをそのまま愛せてゆけ、過去も未来も忘れ、目の前の現実を明るく暮らしてゆける状態が確実にあると思うのです。それも、そうした状況は身に付いているもので、下にはなかなか落ちないで暮らしてゆける状態が。ある意味でいうと、技に近いものだと感じるのです。
いつだったか、どこだったか忘れましたが、ネイティブ・アメリカンかアボリジニだったか忘れましたが「西洋人は皆病んでいる」と言った人がいたそうです。「彼らは、成人しているのに何かを疑う」と。
逆に言えば、彼らは、全てを疑わずにありのままに受け入れて生きてゆけるということでしょう。そうした知恵が技として成人するまでに身に付いているということと理解しました。そうした人々がいるらしいということが私の希望になります。そして、それが本来の成熟すること、成人することなのでしょう。
坐禅は良くなるためにやるのではない、良いとか悪いとかの分別を超えるために坐るというような言葉も頭に浮かびます。私は、様々なことを疑い、概念を弄び、逆に自らの疑念と観念に弄ばれ苦しんできたものと理解しております。文字通り「観念」しなればなりません。未熟なのです。
今はそうした「分別」を乗り越える最中なのです。だから、ギリギリのところで、こうした中途半端な文書が書けるのだと思います。本当に乗り越えてしまったら、こんな文書を書く「分別」はないでしょうから。まだ、自分の苦しみを人におしつけたいという執着が私を捉えているからこそ、こうした半端なものが書けるのです。
第1章 その味噌汁の塩分はいかほど?
~正味の情報量は意外と少ない~
1.1 インスタント味噌汁が商品として存在可能な理由
1.2 人間の手、ドラえもんの手、そしてコンピュータの手
1.3 1杯の味噌汁の中に塩を求めて
1.4 たいへん「ありがたい」お話
1.5 言葉の塩分量を調べてみよう
1.6 まとめ:データとは情報を入れる容器である
Column アナログマンとデジタルマン
第2章 油田のパイプラインと伝言ゲームの連続
~パイプが細けりゃ、通るものも通らない~
2.1 パイプをつなげ! はて、どうやって?
2.2 向こう側とこちら側をつなぐもの
2.3 限界のその向こう側
2.4 濃縮還元な塩水の作り方
2.5 コンピュータには何が見えているか
2.6 まとめ:情報量はわかった、では情報とは?
Column 魔法の塩分計測器・エントロピー
第3章 自動販売機はコンピュータ理解の始まり
~あるいは、自動販売機と人生ゲームのステキな関係~
3.1 自動販売機の気持ちになって考える
3.2 入ってきたお金を覚えよう
3.3 他に似ているものがないか考える
3.4 ちょっと難しく考える:抽象化のキモ
3.5 まとめ:計算機の動きは絶えずして、しかも元の状態にあらず
Column エントロピーのグラフ
第4章 記憶のカースト制
~時間と空間の近さ・遠さ~
4-1 汝のプログラムを愛せよ
4.2 蓄音機の針は踊る
4.3 二兎を追うモノ
4.4 まとめ:メモリは一列でもあり、ピラミッドでもある
第5章 師宣わく「未来は常に移り変わっておる」
~コンピュータの限界とその先~
5.1 チューリングの置き土産
5.2 未来へと続く道
5.3 未来の社会は
5.4 まとめ:未来は常に移り変わっている
Column アプリケーション


